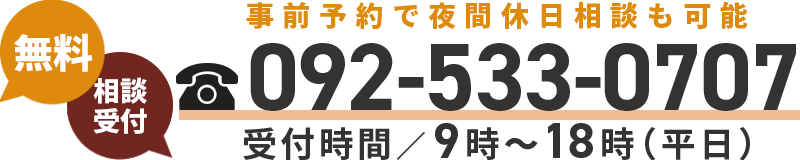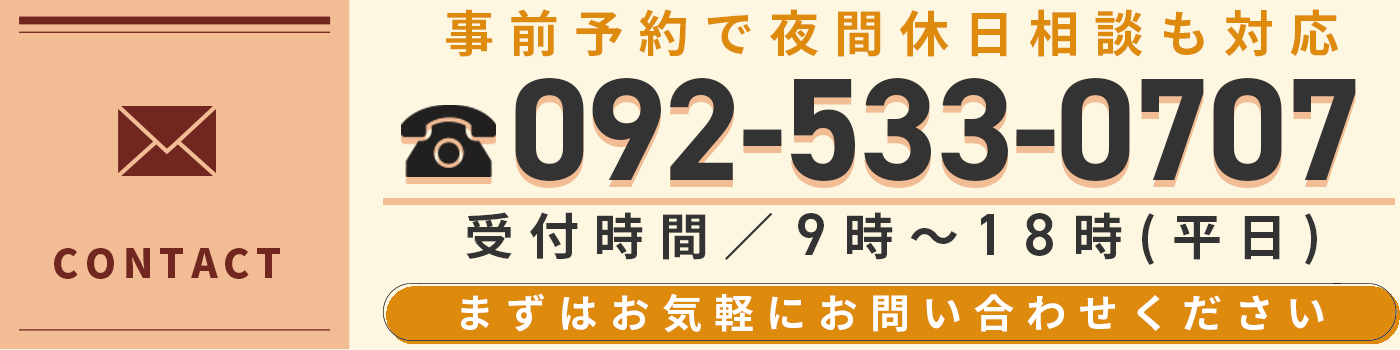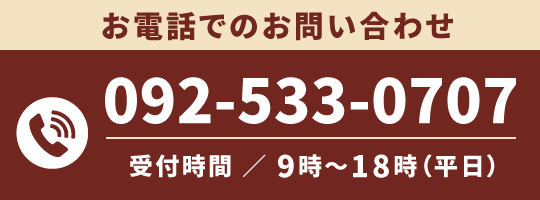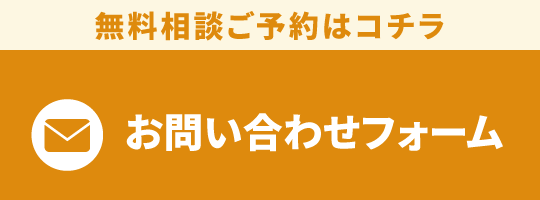このページの目次
はじめに
相続が発生した際、会社から遺族に支給される「弔慰金」や「死亡退職金」について、税務上の取扱いをご存じでしょうか?
実はこれらの給付金には一定の非課税枠が設けられており、制度を正しく理解しておけば相続税の節税につながる可能性があります。
しかし、弔慰金や死亡退職金の非課税・課税の判断基準は複雑で、誤った認識のまま申告してしまうと、思わぬ税負担を強いられることも。
本記事では、税理士の視点から
- 弔慰金と死亡退職金の違い
- 弔慰金が非課税となる条件
- 非課税限度額の計算方法
- 課税対象となるケースとその対応
について、具体的な計算例を交えながらわかりやすく解説します。
なお、弔慰金や退職金の取扱いにお悩みの方は、相続専門の税理士による無料相談もご活用ください。
弔慰金とは?相続税の課税対象ではない理由
弔慰金とは、従業員が亡くなった際に、会社がその遺族に対して支給する金銭で、「労務の対価」ではなく、あくまでもお見舞いの意味合いで支払われるものです。
このため、原則として弔慰金は**相続税の課税対象外(非課税)**となります。
なぜなら、相続税の課税対象は、被相続人の「財産」や「権利」に限られており、死亡後に第三者から支給される弔慰金はこれに該当しないとされるからです。
弔慰金が課税される場合もある?死亡退職金との違いに注意
ただし、支給された金額があまりにも高額な場合は注意が必要です。
国税庁は、「弔慰金」と称していても、その性質や金額からして退職金等の労務対価と判断される部分については、「死亡退職金」とみなして相続税の課税対象としています。
つまり、形式ではなく実質を重視した判断がされるのです。
弔慰金の非課税枠の計算方法
弔慰金の非課税限度額は、死亡が業務上かどうかによって変わります。
| 状況 | 非課税限度額 |
| 業務上の死亡 | 最終月給 × 36ヶ月分 |
| 業務外の死亡 | 最終月給 × 6ヶ月分 |
たとえば、最終月給が50万円だった場合:
- 業務外死亡 → 50万円 × 6 = 300万円
- 業務上死亡 → 50万円 × 36 = 1,800万円
この金額までは「お見舞い金」として非課税。それを超える部分は“実質的な退職金”として相続税の課税対象になるという仕組みです。
具体例で確認!弔慰金と死亡退職金の課税計算
【前提条件】
- 弔慰金として支給:900万円
- 死亡時の月給:50万円
- 死亡は業務外(非業務上)
【計算】
- 弔慰金の非課税限度額:50万円 × 6ヶ月 = 300万円
- 課税対象:900万円 − 300万円 = 600万円
この900万円は、形式的には退職金として扱われ、相続税の対象になります。
死亡退職金にはさらに非課税枠がある
課税される死亡退職金についても、以下のような相続税の非課税枠が設けられています。
死亡退職金の非課税枠:500万円 × 法定相続人の数
たとえば、
- 相続人:配偶者、長男→ 合計2人
- 非課税枠:500万円 × 2 = 1,000万円
前述の例で課税対象となった600万円は、この1,000万円の枠内に収まるため、実際には相続税はかからないという結果になります。
まとめ|正しい理解で相続税を最小限に抑えましょう
弔慰金や死亡退職金の取扱いは、見た目こそ単純そうに見えて、実際は
- 形式ではなく「性質」で判断される
- 非課税の範囲には「複数の基準」がある
- 適切な申告をしなければ税務調査で指摘される可能性がある
という税務上の難所です。
特に、他の財産との関係など実務ではより複雑な判断が求められます。
相続税の申告にあたっては、専門家の判断と助言を仰ぐことが重要です。
おわりに
弔慰金や死亡退職金は、制度を正しく理解して申告すれば、大きな節税につながる可能性があります。
一方で、誤った取扱いをしてしまうと、後になって追徴課税を受けるリスクも。
当事務所では、相続税申告の経験豊富な税理士が、初回無料でのご相談を承っております。
相続に関するお悩みがある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
福岡を中心に北海道から沖縄までの全国を対応しております。
来所又はオンラインによるビデオ電話(Zoomなど)による初回無料相談を実施しております。
当事務所は博多駅から徒歩5分の好立地|税務・経営のお悩みをお気軽にご相談いただけます。
お気軽にお問い合わせください。

福岡市博多区にある久保税理士事務所では、相続税申告や事業承継、生前の節税対策など、個人・法人を問わず幅広いご相談を承っております。
初回のご相談は無料で受け付けておりますので、不安や疑問をお持ちの方も安心してお問い合わせいただけます。
福岡県全域はもちろん、佐賀県、山口県、長崎県、大分県、熊本県など九州各地、さらには全国からのご依頼にも対応可能です。また、オンライン面談にも対応しておりますので、遠方の方もお気軽にご相談ください。