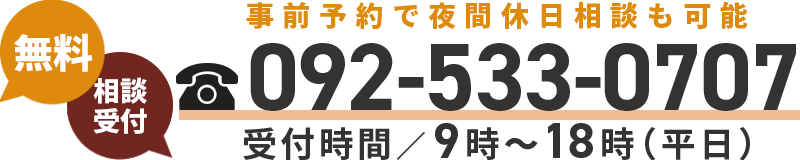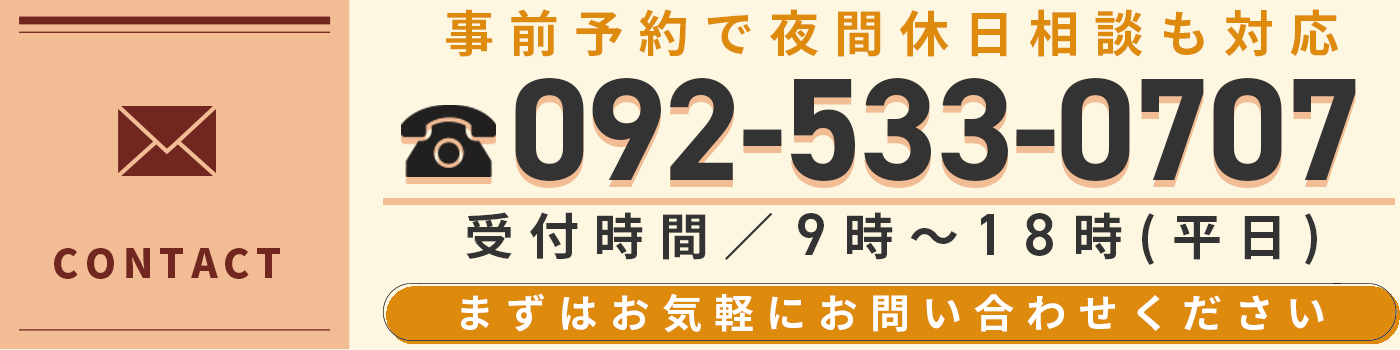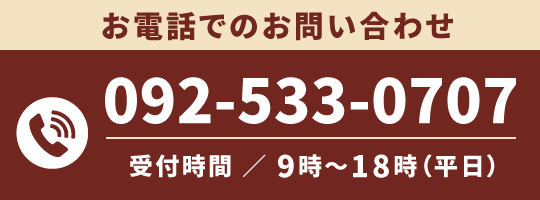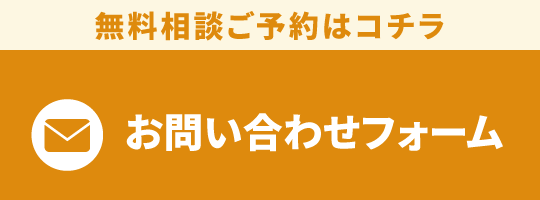このページの目次
はじめに
福岡や熊本でご家族を亡くされた方のもとに、ある日突然「税務署からの手紙」が届くことがあります。タイトルは「相続についてのお尋ね」。聞き慣れない文書名に、戸惑いや不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
しかし、この通知が届いたからといって必ず相続税の申告が必要になるわけではありません。重要なのは、その書類の意味を正しく理解し、適切に対応することです。
今回は、相続手続きにおける「相続についてのお尋ね」の意図や背景、そして福岡・熊本地域の皆さまが安心して手続きを進めるためのポイントを解説します。
「相続についてのお尋ね」とは何か?
この書類は、税務署が「相続税申告の必要があるかどうか」を把握するために送っている文書です。封筒の中には「相続税の申告要否検討表」という記入用紙が同封されており、相続人の人数や相続財産の概要、受け取った保険金などを記入します。
福岡市や熊本市でも、一定以上の財産を持っていた方が亡くなられた場合に送られてくることが多く、すべての相続人に届くものではありません。
税務署はなぜ相続の情報を把握しているのか?
「どうして税務署がうちの財産を知ってるの?」と思われるかもしれませんが、税務署は以下のような情報から故人の資産状況を推測しています。
- 地方自治体から通知される死亡情報
- 所得税の申告記録や源泉徴収票
- 証券会社や金融機関から提出される取引報告書
- 登記情報などの不動産関連データ
- 財産債務調書
こうした情報により、ある程度の財産が確認された場合に「お尋ね」が送られてきます。
「お尋ね」が届いたときの対応
通知は通常、相続発生から6~8か月後に届きます。10か月の申告期限を考えると、準備期間がかなり短くなる可能性もあるため注意が必要です。
1. 無視は避けましょう
提出は義務ではないものの、税務署の目が向いているという意味で、適切な対応が望まれます。特に「相続税はかからない」と自分で判断していても、確認の意味で提出しておく方がリスクを回避できます。
2. 税理士に依頼済みなら回答不要なケースも
既に相続税申告の準備をしている場合は、そのまま税理士を通じて申告すれば問題ありません。
3. 虚偽記載は厳禁です
税務署はすでにある程度の情報を持っています。虚偽の記載は調査に発展し、余計なトラブルを招く可能性があります。
無視した場合のリスク
「書き方がわからないから…」「面倒だから…」と対応を怠ると、以下のようなリスクが生じます。
- 税務調査の対象となるおそれ
- 申告期限を過ぎることで特例・控除が受けられなくなる可能性
- 無申告加算税・延滞税・重加算税などのペナルティが課される
福岡や熊本でも、特に都市部では不動産の評価額が高くなりやすいため、「思ったより課税対象だった」というケースが少なくありません。
届かないからといって安心できない
一方で、「うちには届いてないから大丈夫」と思っている方も要注意です。「お尋ね」が来なくても、申告義務がないとは限りません。基礎控除を超える遺産がある可能性がある場合は、必ず専門家に相談するようにしましょう。
慌てないために、生前からの備えを
相続税申告には相続財産の評価や遺産分割協議など、多くの手続きが必要です。もし「お尋ね」が届いてから申告までの猶予が短い場合、慌ててミスをしてしまうことも。
福岡や熊本で不動産や事業を営んでいる方は、相続が発生する前から「財産目録の作成」「納税資金の確保」などの準備をしておくことをおすすめします。これにより、ご家族が混乱せずにスムーズに手続きを進めることができます。
おわりに
「相続についてのお尋ね」は、相続人を困らせるためのものではなく、税務署が事前に確認を行うための通知です。しかし、その対応を間違えると大きなリスクにも繋がりかねません。
福岡・熊本エリアで相続税に不安を感じている方、突然の「お尋ね」に戸惑っている方は、早めに税理士にご相談ください。専門家のアドバイスを受けることで、安心して相続手続きを進めることができます。
円満で後悔のない相続を実現するためにも、今から備えておくことが大切です。
当事務所では、福岡を中心に北海道から沖縄までの全国を対応しております。
来所又はオンラインによるビデオ電話(Zoomなど)による初回無料相談を実施しております。
当事務所は博多駅から徒歩5分の好立地|税務・経営のお悩みをお気軽にご相談いただけます。
お気軽にお問い合わせください。

福岡市博多区にある久保税理士事務所では、相続税申告や事業承継、生前の節税対策など、個人・法人を問わず幅広いご相談を承っております。
初回のご相談は無料で受け付けておりますので、不安や疑問をお持ちの方も安心してお問い合わせいただけます。
福岡県全域はもちろん、佐賀県、山口県、長崎県、大分県、熊本県など九州各地、さらには全国からのご依頼にも対応可能です。また、オンライン面談にも対応しておりますので、遠方の方もお気軽にご相談ください。