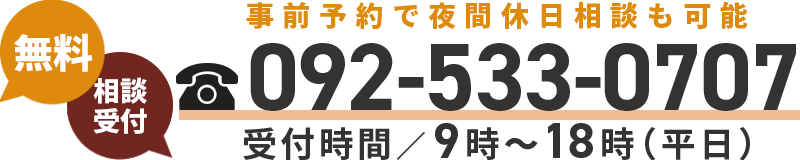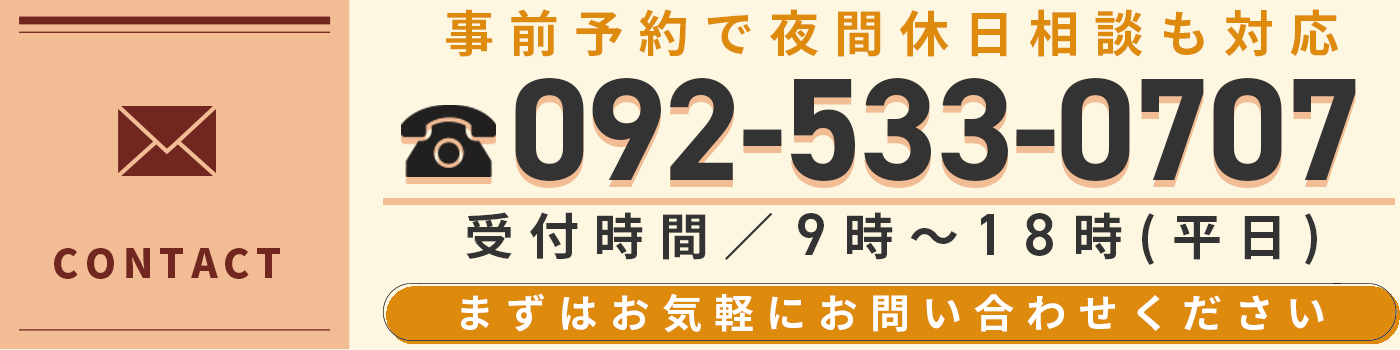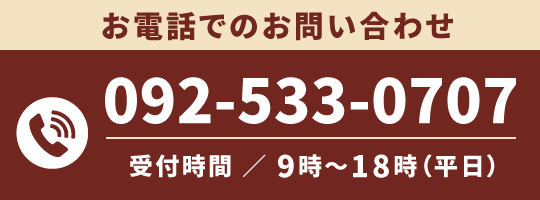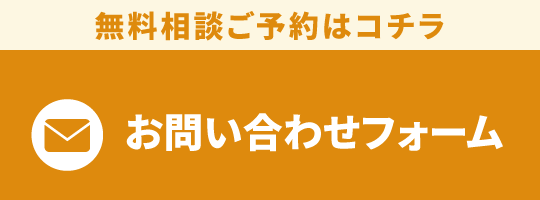このページの目次
はじめに
中小企業の経営者、とりわけ社長が会社の資金繰りを支えるために、自らの個人資産を会社に貸し付けることは決して珍しいことではありません。この「役員借入金」は、会社の財務を支える重要な資金である一方で、経営者の死亡によって「相続財産」としてカウントされる点に注意が必要です。
実は、相続税の計算において、役員借入金の存在が相続人にとって大きな負担となることがあります。また、返済義務を負う会社側も同時に資金繰りに窮する恐れがあり、二重のリスクを抱える形になります。
この記事では、役員借入金が相続税に与える影響や、相続時に問題となる理由、そして実際にどのような対策が可能かを、無料相談を活用しながら具体的にご紹介します。
役員借入金とは?相続税の対象になる理由
「役員借入金」とは、社長や取締役などの会社役員が、会社に対して個人資産を貸し付けた金銭を指します。帳簿上は会社の負債であり、役員側から見れば「会社に対する債権(財産)」です。
つまり、経営者が亡くなった際には、この役員借入金は相続財産として扱われ、一定額を超えれば相続税の課税対象になります。
具体例
たとえば、会社に対する貸付金が5,000万円あるとします。他に現金や不動産などの財産と合算して、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えると、課税される相続財産となります。
相続税の納税資金が手元にない場合、相続人は金融機関からの借入や不動産の売却を検討せざるを得ない状況に追い込まれかねません。
【例外】相続財産とみなされないケースもある?
役員借入金が常に相続税の課税対象になるわけではありません。以下のような例外的ケースでは、課税対象から除外される可能性があります。
- 会社が既に破産・民事再生など法的手続きに入っており、貸付金の回収見込みが完全にないと判断できる場合
- 実質的に債権が回収不可能であり、かつ税務上も「評価不能資産」として取り扱われるケース
とはいえ、「経営が厳しい」「赤字が続いている」といった事情のみでは認められません。証拠となる財務資料や第三者評価の提示が必要になるため、専門家との相談が不可欠です。
相続税を軽減する!役員借入金を減らす4つの方法
相続が発生する前に、役員借入金を節税対策として計画的に整理しておくことが肝心です。以下に、実際の実務でも多く活用されている4つの方法をご紹介します。
1. 債権放棄を行う
役員自身の意思で、貸付金の一部または全部を放棄する方法です。
メリット
- 相続財産から除外されるため、相続税の課税額を減らせる
- 放棄された金額は、会社の「債務免除益」となり、繰越欠損金があれば税負担ゼロで処理可能
注意点
債権放棄で株価が上昇すると、他の株主に対する「みなし贈与」が発生し、贈与税のリスクが生じます
2. 役員報酬を減額し、借入金返済に充当する
報酬を意図的に減額し、その分の資金を借入金返済にまわす方法です。
メリット
- 会社の負担は実質変わらず、返済が可能
- 所得税や住民税の負担も軽減される
注意点
役員報酬は原則として年度中に変更できないため、事前の計画が必要です
3. DES(デット・エクイティ・スワップ)の活用
貸付金を資本金へ振り替える方法です。
メリット
- 借入金が会社の「純資産」に変化し、返済義務が消滅
- 経営者が取得した株式には、将来の事業承継税制の活用余地も
注意点
債務超過の会社ではDESを実施できないケースがあります
4. 相続人に対する生前贈与
相続税が重くなることを見越して、後継者に貸付金を生前贈与する方法です。
メリット
贈与税の年間非課税枠(110万円)を利用し、複数年かけて贈与すれば節税可能
注意点
- 令和5年度の税制改正で、贈与加算期間が7年に延長されました。相続人への贈与は早期に実行すべきです
- 相続人以外(例:孫など)への贈与であれば、加算対象から除外される可能性があります
無料相談で最適な選択肢を一緒に検討しませんか?
役員借入金の処理は、単に税金の問題にとどまらず、会社の今後の経営にも直結する重大なテーマです。さらに、相続人の納税資金の確保や相続トラブルの防止のためにも、早めの対策が必要不可欠です。
久保税理士事務所では、相続税と法人経営を熟知した専門家が、役員借入金の整理や相続税対策のご相談を無料で承っております。
- 自社の貸借対照表に「役員借入金」が残っている
- 経営者が高齢で将来的に相続が心配
- 相続税の納税資金が準備できるか不安
- DESや債権放棄などの実施可能性を検討したい
このような方は、ぜひ一度ご相談ください。
おわりに
「会社のために貸し付けた資金」が、相続税という形で家族に重くのしかかる――これは多くの経営者にとって見逃せないリスクです。
会社の存続と家族の将来を守るためにも、役員借入金の整理は節税対策として計画的に行うことが重要です。状況によっては、数百万円単位で相続税が変動することもあります。
どの方法が適切かは、会社の財務状況や経営者の年齢・家族構成によって異なります。ぜひ、税理士との専門的な相談を通じて、最良の選択を見つけてください。
当事務所では、福岡を中心に北海道から沖縄までの全国を対応しております。
来所又はオンラインによるビデオ電話(Zoomなど)による初回無料相談を実施しております。
当事務所は博多駅から徒歩5分の好立地|税務・経営のお悩みをお気軽にご相談いただけます。
お気軽にお問い合わせください。

福岡市博多区にある久保税理士事務所では、相続税申告や事業承継、生前の節税対策など、個人・法人を問わず幅広いご相談を承っております。
初回のご相談は無料で受け付けておりますので、不安や疑問をお持ちの方も安心してお問い合わせいただけます。
福岡県全域はもちろん、佐賀県、山口県、長崎県、大分県、熊本県など九州各地、さらには全国からのご依頼にも対応可能です。また、オンライン面談にも対応しておりますので、遠方の方もお気軽にご相談ください。