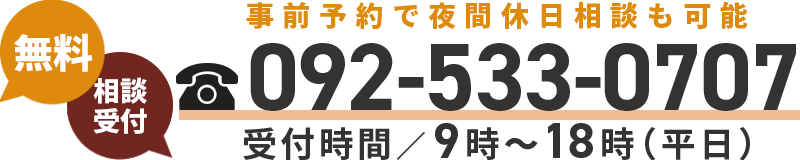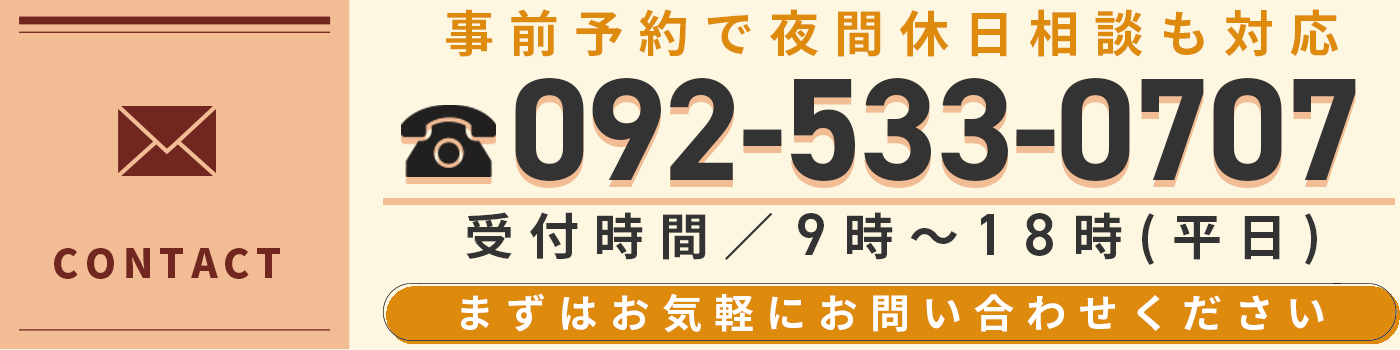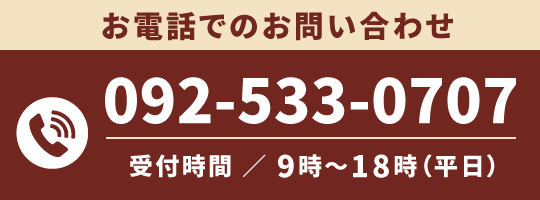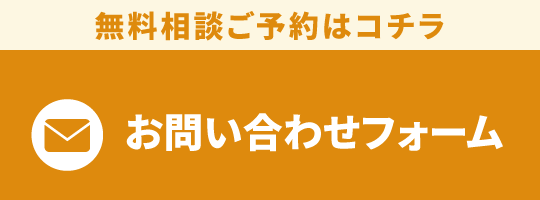Author Archive
弔慰金は相続税の対象?非課税になる条件と金額の計算方法を解説
はじめに
相続が発生した際、会社から遺族に支給される「弔慰金」や「死亡退職金」について、税務上の取扱いをご存じでしょうか?
実はこれらの給付金には一定の非課税枠が設けられており、制度を正しく理解しておけば相続税の節税につながる可能性があります。
しかし、弔慰金や死亡退職金の非課税・課税の判断基準は複雑で、誤った認識のまま申告してしまうと、思わぬ税負担を強いられることも。
本記事では、税理士の視点から
- 弔慰金と死亡退職金の違い
- 弔慰金が非課税となる条件
- 非課税限度額の計算方法
- 課税対象となるケースとその対応
について、具体的な計算例を交えながらわかりやすく解説します。
なお、弔慰金や退職金の取扱いにお悩みの方は、相続専門の税理士による無料相談もご活用ください。
(さらに…)
福岡市博多区にある久保税理士事務所では、相続税申告や事業承継、生前の節税対策など、個人・法人を問わず幅広いご相談を承っております。
初回のご相談は無料で受け付けておりますので、不安や疑問をお持ちの方も安心してお問い合わせいただけます。
福岡県全域はもちろん、佐賀県、山口県、長崎県、大分県、熊本県など九州各地、さらには全国からのご依頼にも対応可能です。また、オンライン面談にも対応しておりますので、遠方の方もお気軽にご相談ください。
相続税申告で建物更生共済(建更)がある場合の注意点と実務ポイント
はじめに
相続税申告の際、被相続人がJA共済(農協系)の建物更生共済(建更/たてこう)に加入していた場合、通常の火災保険や地震保険とは異なる独特な税務取扱いが必要になることをご存知でしょうか。
契約者・掛金負担者・建物所有者(被共済者)の組み合わせ次第で、相続税の課税額や評価方法が大きく変わるため、事前の正確な判断が欠かせません。
「建更があるけど、どう申告すればいいのかわからない」
「評価額の根拠をどうやって取得すればいいの?」
そんな疑問をお持ちの方は、申告期限に余裕があるうちに専門家へご相談ください。初回相談は無料で行っています。

福岡市博多区にある久保税理士事務所では、相続税申告や事業承継、生前の節税対策など、個人・法人を問わず幅広いご相談を承っております。
初回のご相談は無料で受け付けておりますので、不安や疑問をお持ちの方も安心してお問い合わせいただけます。
福岡県全域はもちろん、佐賀県、山口県、長崎県、大分県、熊本県など九州各地、さらには全国からのご依頼にも対応可能です。また、オンライン面談にも対応しておりますので、遠方の方もお気軽にご相談ください。
【医療法人】出資持分の相続税評価を引き下げる5つの方法とは?
はじめに
医療法人の理事長やご家族の方から「出資持分の評価が高すぎて相続税が高額になるのではないか」といったご相談をいただくことがあります。
医療法人の出資持分は、配当や自由な運用が制限される一方で、相続税評価額が非常に高くなりやすいという特徴があります。特に、長年黒字経営を続けてきた医療法人ほど、出資持分の評価額が高額になることも珍しくありません。
しかし、適切な対策を講じることで、この出資持分評価を大きく引き下げることが可能です。
本記事では、医療法人の出資持分評価が高額となる理由から、その引き下げ方法までを解説します。
相続対策にお悩みの方は、初回無料相談をぜひご利用ください。
(さらに…)
福岡市博多区にある久保税理士事務所では、相続税申告や事業承継、生前の節税対策など、個人・法人を問わず幅広いご相談を承っております。
初回のご相談は無料で受け付けておりますので、不安や疑問をお持ちの方も安心してお問い合わせいただけます。
福岡県全域はもちろん、佐賀県、山口県、長崎県、大分県、熊本県など九州各地、さらには全国からのご依頼にも対応可能です。また、オンライン面談にも対応しておりますので、遠方の方もお気軽にご相談ください。
【税理士が解説】福岡の地価上昇と相続税|2025年路線価から見る今後の対策
はじめに
2025年7月1日、国税庁から令和7年分の相続税・贈与税に関する路線価が公表されました。全国約32万地点の評価額が更新されるこの指標は、相続税や贈与税の基礎となる「土地の評価額」に直結する極めて重要な基準です。
中でも注目を集めているのが福岡県の地価動向です。
福岡県は、地価の上昇率で全国第3位となり、将来的な相続税の負担増加が避けられない状況になりつつあります。
本記事では、福岡県の最新路線価データをもとに、相続税・贈与税への影響と、今すぐに取り組むべき対策の方向性を詳しく解説します。
(さらに…)
福岡市博多区にある久保税理士事務所では、相続税申告や事業承継、生前の節税対策など、個人・法人を問わず幅広いご相談を承っております。
初回のご相談は無料で受け付けておりますので、不安や疑問をお持ちの方も安心してお問い合わせいただけます。
福岡県全域はもちろん、佐賀県、山口県、長崎県、大分県、熊本県など九州各地、さらには全国からのご依頼にも対応可能です。また、オンライン面談にも対応しておりますので、遠方の方もお気軽にご相談ください。
相続税の障害者控除とは?適用要件・計算方法・申告不要のケースを解説
はじめに
相続税の申告では、「障害者控除」という制度を利用することで、相続税の負担を大幅に軽減できる場合があります。
しかし実務上、障害者控除の申告漏れは少なくありません。実際、適用できたにもかかわらず、控除を受けずに申告してしまい、本来より多額の税金を納めてしまった事例もあります。
特に「障害者控除を使えば相続税がゼロになる」「申告すら不要になる」ケースがあることは、一般の方にはあまり知られていません。
本記事では、障害者控除の適用要件から計算方法、具体的なケーススタディ、そして申告不要となる例や更正の手続きまで、税理士が分かりやすく丁寧に解説いたします。
(さらに…)
福岡市博多区にある久保税理士事務所では、相続税申告や事業承継、生前の節税対策など、個人・法人を問わず幅広いご相談を承っております。
初回のご相談は無料で受け付けておりますので、不安や疑問をお持ちの方も安心してお問い合わせいただけます。
福岡県全域はもちろん、佐賀県、山口県、長崎県、大分県、熊本県など九州各地、さらには全国からのご依頼にも対応可能です。また、オンライン面談にも対応しておりますので、遠方の方もお気軽にご相談ください。
相続税の納付書はどこでもらう?必要な手続きと記入の注意点まとめ
はじめに:相続税の納税で「納付書をもらっていない」は通用しません
親や配偶者が亡くなり、相続が発生した際、相続税の申告と納付が必要になるケースがあります。
ところが、多くの方が見落としがちなのが「納付書の準備」。固定資産税のように郵送されてくるものと思っていると、相続税では納付期限を過ぎてしまう恐れがあります。
本記事では、相続税の納付書のもらい方、正しい書き方、そして納付方法について、相続専門の税理士が徹底的に解説します。
納付期限を過ぎて延滞税が発生する前に、この記事を読んで確実に準備を整えておきましょう。

福岡市博多区にある久保税理士事務所では、相続税申告や事業承継、生前の節税対策など、個人・法人を問わず幅広いご相談を承っております。
初回のご相談は無料で受け付けておりますので、不安や疑問をお持ちの方も安心してお問い合わせいただけます。
福岡県全域はもちろん、佐賀県、山口県、長崎県、大分県、熊本県など九州各地、さらには全国からのご依頼にも対応可能です。また、オンライン面談にも対応しておりますので、遠方の方もお気軽にご相談ください。
「控除できるなんて知らなかった…」相続税申告で見逃されがちな医療費の扱い
はじめに
相続税申告にあたり、債務控除という制度をご存じでしょうか?
債務控除とは、被相続人(亡くなった方)が亡くなる時点で負っていた借金や未払金などを、相続財産から差し引くことができる制度です。この控除を適切に活用することで、相続税の負担を大幅に軽減できる可能性があります。
今回は、家族が生前に立て替えていた医療費なども、この債務控除の対象となるのかどうかを詳しく解説いたします。実は、相続人の方も税理士も見落としがちな重要ポイントなのです。
(さらに…)
福岡市博多区にある久保税理士事務所では、相続税申告や事業承継、生前の節税対策など、個人・法人を問わず幅広いご相談を承っております。
初回のご相談は無料で受け付けておりますので、不安や疑問をお持ちの方も安心してお問い合わせいただけます。
福岡県全域はもちろん、佐賀県、山口県、長崎県、大分県、熊本県など九州各地、さらには全国からのご依頼にも対応可能です。また、オンライン面談にも対応しておりますので、遠方の方もお気軽にご相談ください。
相続税の申告前に要確認!知らなきゃ損する「葬儀費用の控除」ガイド
はじめに:知らなきゃ損する「葬儀費用の控除」
相続税の申告では、「葬儀費用」を適切に控除することで、相続税額を大幅に減らせる可能性があります。
実際、葬儀にかかる費用は100万円~200万円にのぼるケースも珍しくありません。これらが適正に控除できれば、数十万円単位で税額に差が出ることもあります。
しかし、「どの費用が控除対象になるのか」を正しく理解していないと、控除漏れにより結果的に多くの税金を支払ってしまう可能性もあるのです。
本記事では、国税庁のホームページに基づきながら、相続税の計算において「控除できる葬儀費用」と「控除できない葬儀費用」の違いや注意点をわかりやすく解説していきます。

福岡市博多区にある久保税理士事務所では、相続税申告や事業承継、生前の節税対策など、個人・法人を問わず幅広いご相談を承っております。
初回のご相談は無料で受け付けておりますので、不安や疑問をお持ちの方も安心してお問い合わせいただけます。
福岡県全域はもちろん、佐賀県、山口県、長崎県、大分県、熊本県など九州各地、さらには全国からのご依頼にも対応可能です。また、オンライン面談にも対応しておりますので、遠方の方もお気軽にご相談ください。
自社株の相続でお悩みの経営者様へ|相続税・事業承継の無料相談受付中
はじめに:自社株対策を怠ると「会社ごと潰れる」可能性も?
会社を経営されているオーナー社長の皆さま、自社株に対する相続税対策はお済みでしょうか?
「自社株は売れないのに、莫大な相続税がかかる」
「資産の多くが会社に集中していて、納税資金が用意できない」
このようなお悩みを抱えたまま、対策をせずに放置してしまうと、ご自身の死後、ご家族が納税資金を工面できず、会社の経営や存続に深刻な影響を及ぼしかねません。
本コラムでは、**なぜ自社株に相続税対策が必要なのか?**という根本的な視点から、具体的な評価方法と節税対策の実践方法について、税理士の視点からわかりやすく解説します。
自社株評価や相続対策でお悩みの方は、ぜひ最後までお読みください。
(さらに…)
福岡市博多区にある久保税理士事務所では、相続税申告や事業承継、生前の節税対策など、個人・法人を問わず幅広いご相談を承っております。
初回のご相談は無料で受け付けておりますので、不安や疑問をお持ちの方も安心してお問い合わせいただけます。
福岡県全域はもちろん、佐賀県、山口県、長崎県、大分県、熊本県など九州各地、さらには全国からのご依頼にも対応可能です。また、オンライン面談にも対応しておりますので、遠方の方もお気軽にご相談ください。
相続税を減らすには相続人を増やす?養子縁組を使った節税戦略
はじめに
「長年連れ添ったパートナーに財産を残したいが、血縁関係がないため相続権がない」
「子どもがいないため、自分の意思で財産を託せる仕組みを考えておきたい」
このようなお悩みをお持ちの方にとって、養子縁組という制度は、相続上の選択肢として非常に有効です。
養子縁組は、法律上の親子関係を築くことで、実子と同じように法定相続人としての地位を与えることができる制度です。さらに、この仕組みを上手に活用することで、相続税の節税にもつながる可能性があります。
この記事では、養子縁組による相続税対策のメリットや注意点、普通養子縁組と特別養子縁組の違いなどをわかりやすく解説いたします。
相続対策として養子縁組を検討されている方、血縁関係にない方へ財産を残したいと考えている方は、ぜひ最後までご一読ください。

福岡市博多区にある久保税理士事務所では、相続税申告や事業承継、生前の節税対策など、個人・法人を問わず幅広いご相談を承っております。
初回のご相談は無料で受け付けておりますので、不安や疑問をお持ちの方も安心してお問い合わせいただけます。
福岡県全域はもちろん、佐賀県、山口県、長崎県、大分県、熊本県など九州各地、さらには全国からのご依頼にも対応可能です。また、オンライン面談にも対応しておりますので、遠方の方もお気軽にご相談ください。