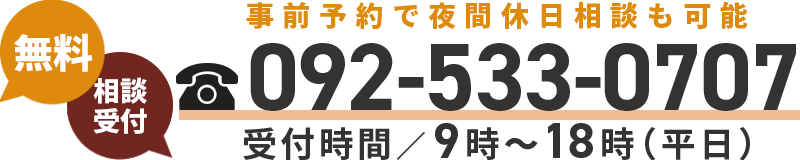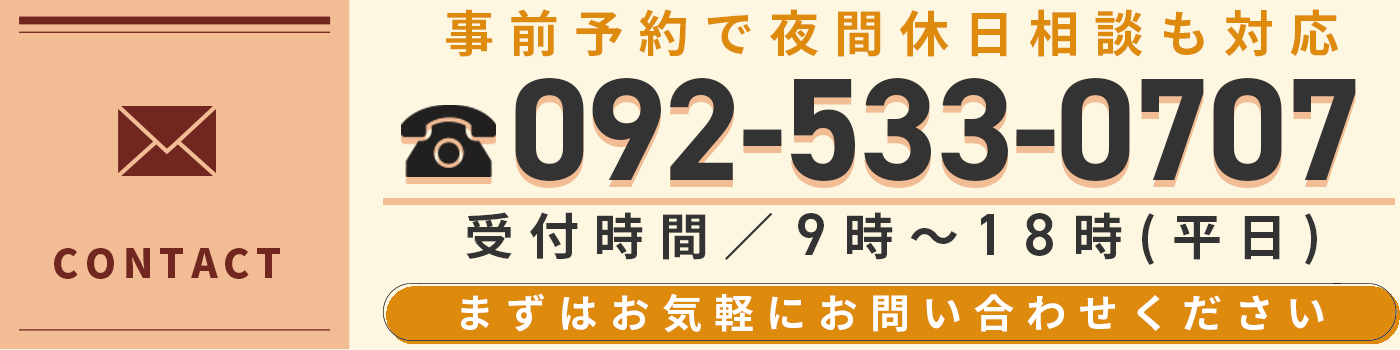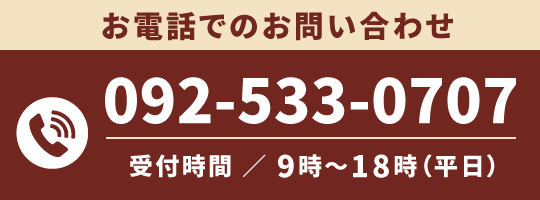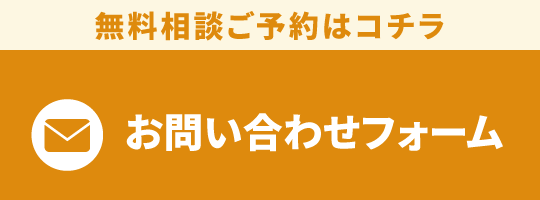このページの目次
はじめに:知らなきゃ損する「葬儀費用の控除」
相続税の申告では、「葬儀費用」を適切に控除することで、相続税額を大幅に減らせる可能性があります。
実際、葬儀にかかる費用は100万円~200万円にのぼるケースも珍しくありません。これらが適正に控除できれば、数十万円単位で税額に差が出ることもあります。
しかし、「どの費用が控除対象になるのか」を正しく理解していないと、控除漏れにより結果的に多くの税金を支払ってしまう可能性もあるのです。
本記事では、国税庁のホームページに基づきながら、相続税の計算において「控除できる葬儀費用」と「控除できない葬儀費用」の違いや注意点をわかりやすく解説していきます。
相続税の計算上、控除できる葬儀費用とは?
国税庁では、相続税の計算において控除可能な葬儀費用として、以下のような支出を認めています。
控除できる主な費用の一覧(具体例)
| 項目 | 内容 |
| 死亡診断書発行費用 | 医師による死亡診断書の作成料など |
| 通夜・告別式関連費用 | 会場費、参列者への飲食代、受付用備品など |
| 供花・供物費用 | 相続人が喪主として負担したものに限る |
| 遺体搬送費用 | 自宅から葬儀場、火葬場などへの移送 |
| 火葬・埋葬費用 | 火葬料、埋葬料、納骨にかかる費用 |
| 僧侶へのお布施 | 読経料、戒名料、車代など含む |
| 葬儀手伝いへの心付け | 葬儀社以外の親戚・知人へのお礼 |
領収書がない費用の取り扱い
中には、心付けや僧侶へのお布施など、領収書が発行されないものもあります。
そのような場合でも、以下の内容を明記した「支出メモ」を作成すれば申告時の証明資料として利用できます。
- 支出の内容
- 支払日
- 金額
- 相手方の名前または団体名
このようなメモがあるだけで、税務調査に対しても説明しやすくなります。
相続税の計算上、控除できない葬儀費用とは?
反対に、控除が認められない費用もあります。これは「葬儀に直接関係しない」「今後の宗教的行事に関する」支出が中心です。
控除できない費用の例
| 項目 | 内容 |
| 香典返し | お礼の品や発送費用など |
| 墓地・墓石の購入費用 | 墓地の取得や永代供養料も含む |
| 法事の費用 | 初七日、四十九日、一周忌など |
| 位牌の購入費用 | 仏壇に安置する「本位牌」の費用 |
| 彫刻費用 | 墓石や位牌への名入れ代など |
| 医学的・裁判的対応費用 | 解剖、DNA鑑定など特別な費用 |
よくある誤解と補足
- 「会葬御礼」のような葬儀当日の返礼品は控除対象です。
- 白木の位牌(仮位牌)は葬儀に必要なものであるため、控除対象になります。
- 本位牌や仏壇は「今後の供養」に関わるものであるため、対象外です。
互助会の積立金がある場合の注意点
最近では、葬儀の準備として「互助会」に加入して積立をしている方も多くいらっしゃいます。
この積立金を充当して葬儀費用の一部を支払った場合でも、以下のような処理が必要です。
- 積立金が被相続人の財産である場合 → 相続財産として加算
- 葬儀費用全体 → 控除対象として申告可能
つまり、積立金をいったん「プラスの相続財産」として計上し、その上で「マイナスの葬儀費用」として控除する、という2段階処理が必要です。
相続税のプロが伝えたいポイント(まとめ)
- 葬儀に関する支出はすべてが控除できるわけではありません。
- 適切に控除すれば相続税の軽減効果は非常に大きくなります。
- 領収書がない費用も正しい方法で申告すれば問題ありません。
しかし、こうした判断は一般の方には非常に複雑で、誤って損をしているケースも多く見られます。
例えば、香典返しや墓地購入費用などを控除対象だと思い込んでしまい、税務署からの指摘を受けるケースもあるのです。
おわりに:相続税申告は専門家への相談が安心・確実です
相続は人生の中で何度も経験することではありません。だからこそ「何が正しく、何が損になるのか」を判断するのは簡単ではありません。
当事務所では、相続税に特化した専門の税理士が、豊富な実務経験と最新の法令知識に基づき、
丁寧なサポートを行っております。
初回のご相談は無料ですので、「こんな費用は控除できるの?」「申告に不安がある」など、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
福岡を中心に北海道から沖縄までの全国を対応しております。
来所又はオンラインによるビデオ電話(Zoomなど)による初回無料相談を実施しております。
当事務所は博多駅から徒歩5分の好立地|税務・経営のお悩みをお気軽にご相談いただけます。
お気軽にお問い合わせください。

福岡市博多区にある久保税理士事務所では、相続税申告や事業承継、生前の節税対策など、個人・法人を問わず幅広いご相談を承っております。
初回のご相談は無料で受け付けておりますので、不安や疑問をお持ちの方も安心してお問い合わせいただけます。
福岡県全域はもちろん、佐賀県、山口県、長崎県、大分県、熊本県など九州各地、さらには全国からのご依頼にも対応可能です。また、オンライン面談にも対応しておりますので、遠方の方もお気軽にご相談ください。