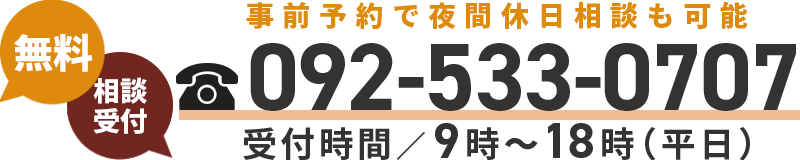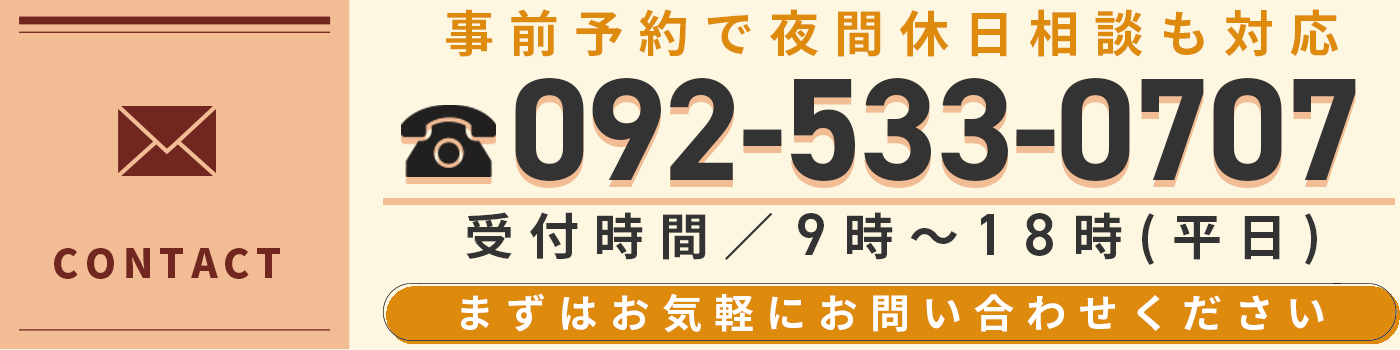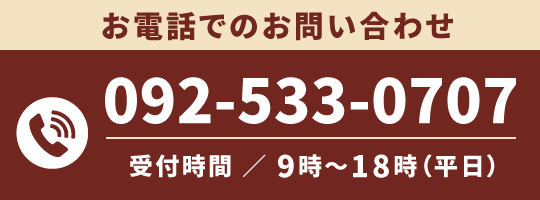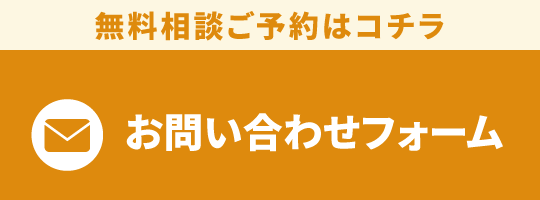このページの目次
はじめに
国税庁が公表した令和5年分(2023年)の「相続税の申告事績」によれば、相続の発生件数は1,576,016件、そのうち相続税の申告書が提出されたのは155,740件で、課税割合は9.9%。つまり、亡くなった方の約10人に1人が相続税の申告対象になっています。
また、相続税を実際に納税した相続人は339,098人にのぼり、課税価格の総額は21兆6,335億円、税額は3兆53億円。
被相続人1人あたりの課税価格は1億3,891万円、税額は1,930万円という高額な結果になりました。
財産の内訳を見ると、最も多いのが「現金・預貯金」で7兆9,633億円。
続いて土地(7兆1,425億円)、有価証券(3兆8,779億円)、家屋(1兆1,452億円)、その他(2兆5,817億円)という構成です。
これらのデータからも、相続税が「一部の富裕層だけの税金」ではなく、広く一般家庭にも関係する「身近な税」となりつつある現状が見えてきます。
相続税の課税件数は年々増加している
平成27年の相続税法改正で基礎控除が縮小されて以降、申告件数は右肩上がりに増えています。
- 令和4年:150,858件
- 令和5年:155,740件(前年比103.2%)
死亡者数の増加に加え、地価や株価の上昇によって相続財産の評価額が上がり、申告対象となる人が増えていると考えられます。
税務調査の実態|「簡易な接触」が急増中
相続税の課税対象者が増加するなか、税務調査の件数も増加傾向にあります。
国税庁が発表した令和5年(2023年)事務年度の「相続税の調査実績」によると、調査件数は前年比17.8%増の27,337件に達しました。
特に注目すべきは、「簡易な接触」の増加です。
従来の「実地調査」ではなく、文書照会・電話・税務署への来所要請などを活用した柔軟な調査方法が主流となっており、令和5年は実地調査の2.2倍にも上る件数が実施されました。
さらに、税務署ではAIを活用して調査対象者の絞り込みを進めており、今後も調査件数は増加する見込みです。
相続税については、「税務署に見つからなければいい」という考え方は通用しません。事前の対策と適切な申告が重要です。
相続税対策には現金比率の見直しや生前贈与が有効
現金・預貯金は評価額=そのまま課税対象となるため、税負担が大きくなりがちです。
- 不動産活用:不動産は評価額が時価の70〜80%程度で済みます
- 生前贈与:年間110万円までの暦年贈与や、教育資金贈与・結婚資金贈与などの非課税制度を活用
ただし、生前贈与には贈与税がかかる可能性もあるため、相続税とのバランスを考えた対策が必要です。
相続税申告の「e-Tax」利用はまだ37.1%
相続税の電子申告システム「e-Tax」は便利でありながら、利用率はまだ37.1%にとどまっています。
法人税(86.2%)、所得税(69.3%)などと比べると、相続税の利用率は低いです。
今後、e-Taxの普及によって申告の効率化・誤りの減少が期待されています。
おわりに
相続税は「お金持ちだけの話」ではなくなっています。申告件数は増加し、税務調査もAI導入によって効率化が進み、ますます厳しくなっています。
さらに、現金比率の高い財産構成など、準備をしていなかったことで余分な税負担が発生するリスクも存在します。
「相続が起こる前に、何をしておくべきか?」
「うちの財産は相続税の対象になるのか?」
そういった疑問をお持ちの方は、早めのご相談がトラブル回避と節税の第一歩です。
どうぞお気軽にご相談ください。
当事務所では、福岡を中心に北海道から沖縄までの全国を対応しております。
来所又はオンラインによるビデオ電話(Zoomなど)による初回無料相談を実施しております。
当事務所は博多駅から徒歩5分の好立地|税務・経営のお悩みをお気軽にご相談いただけます。
※本記事は国税庁「令和5年分 相続税の申告実績の概要」および「相続税の調査実績の概要」を参考に作成しております。
具体的なご相談は、相続税に精通した専門の税理士へご連絡ください。

福岡市博多区にある久保税理士事務所では、相続税申告や事業承継、生前の節税対策など、個人・法人を問わず幅広いご相談を承っております。
初回のご相談は無料で受け付けておりますので、不安や疑問をお持ちの方も安心してお問い合わせいただけます。
福岡県全域はもちろん、佐賀県、山口県、長崎県、大分県、熊本県など九州各地、さらには全国からのご依頼にも対応可能です。また、オンライン面談にも対応しておりますので、遠方の方もお気軽にご相談ください。