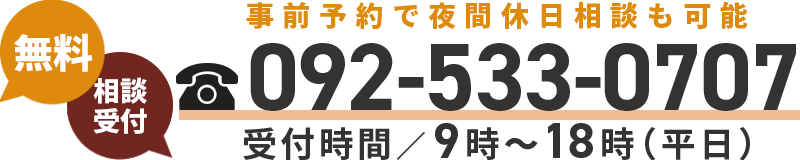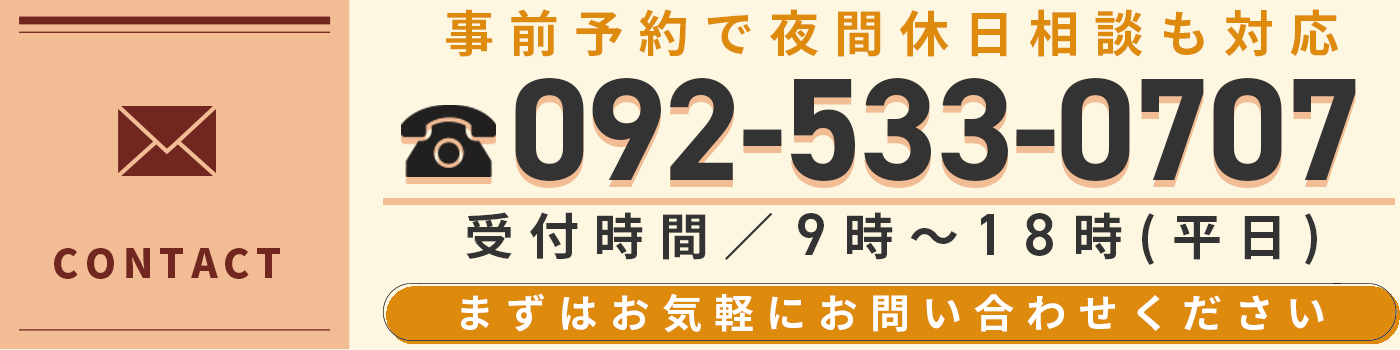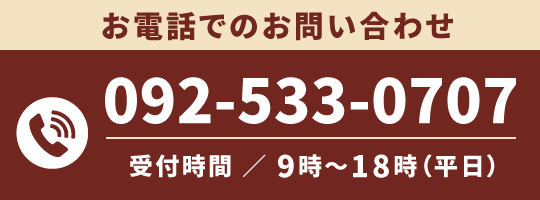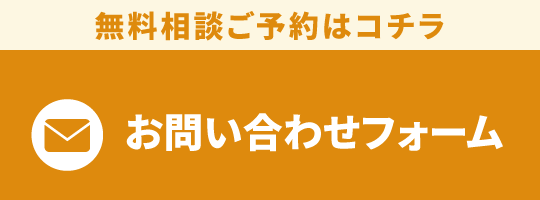このページの目次
はじめに
相続が発生すると、ご遺族の皆様は遺産分割の話し合いを進めながら、相続税の申告や納税の準備を行う必要があります。
しかし、相続人同士の意見が分かれたり、不動産などの分け方で揉めたりすることで、遺産分割協議が長引いてしまうケースは珍しくありません。
特に相続税には「申告期限(原則10ヶ月以内)」が法律で定められており、遺産分割がまとまらないことを理由にこの期限を延長することはできません。
今回は、遺産分割が成立しないまま申告期限を迎える場合にどのような影響があるのか、そして事前に取れる対策について解説します。
相続税の申告期限と納付期限の基本
相続税の申告と納税は、被相続人が亡くなったことを知った日(通常は死亡日)から10ヶ月以内に行わなければなりません。
この期限は法律で定められているもので、基本的には遺産分割が進んでいない場合でも延長は認められません。
例外的に、災害や新型コロナウイルス感染症の影響など「やむを得ない事情」がある場合には、税務署へ申請することで申告期限の延長が認められることもあります。
しかし、遺産分割協議がまとまらないという理由は「やむを得ない事情」には該当しない点に注意が必要です。
遺産分割がまとまらない場合の相続税の計算方法
遺産分割が成立しないまま申告期限を迎えた場合、各相続人は「法定相続分」に従って遺産を取得したものとみなされて相続税が計算されます。
法定相続分とは?
民法に定められた各相続人が取得する割合のことです。
(1)配偶者と子どもが相続人となる場合
相続財産は、まず配偶者と子どもで半分ずつ(2分の1ずつ)分けるのが基本です。
子どもが複数いる場合には、その子どもが取得する2分の1の財産を人数で均等に分けることになります。
【具体例】
相続人:配偶者と子ども2人の場合
→ 配偶者が2分の1、子どもは残りの2分の1を2人で均等に分割(それぞれ4分の1ずつ)
(2)配偶者と直系尊属(父母や祖父母)が相続人となる場合
この場合、相続財産のうち3分の2は配偶者が取得し、残りの3分の1を直系尊属(父母や祖父母)が取得します。
直系尊属が複数いる場合は、親等の近い人(通常は父母)が優先されます。もし同じ親等で複数人いる場合は、均等に分けることになります。
【具体例】
相続人:配偶者と父母(2人)の場合
→ 配偶者が3分の2、父母は残りの3分の1を均等に(それぞれ6分の1ずつ)
(3)配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合
このケースでは、配偶者が全体の4分の3を相続し、兄弟姉妹が残りの4分の1を人数で均等に分けます。
ただし、兄弟姉妹の相続分については、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1となります。
【具体例】
相続人:配偶者と兄弟3人(うち1人は異母兄弟)の場合
→ 配偶者が4分の3、残りの4分の1を父母同一の兄弟2人と異母兄弟1人で分けるが、異母兄弟は相続分が半分になる。
この割合を前提に相続税の計算と納税が行われるため、実際の分割内容が異なる場合には、後日「修正申告」や「更正の請求」が必要になることもあります。
遺産分割が成立しないことで受けられない主な特例
遺産分割協議が成立していないと、相続税の軽減措置や特例が適用できなくなるケースがあります。
その代表的なものが以下の4つです。
① 配偶者に対する相続税額の軽減
配偶者が相続する財産のうち、法定相続分または1億6,000万円までのいずれか多い金額については相続税がかからない制度です。
遺産分割協議が成立していないと、この特例は適用できません。
② 小規模宅地等の特例
自宅や事業用の土地について評価額を大幅に減額できる制度です。
適用するには「誰がその土地を取得したか」が明確である必要があるため、未分割の状態では使えません。
③ 納税猶予制度
農地や非上場株式などを相続した場合に、一定の要件を満たせば相続税の納税を猶予できる制度です。これも取得者が決まっていなければ適用できません。
④ 物納制度
金銭で相続税の納付が困難な場合に、不動産や有価証券で納付する方法ですが、遺産分割協議が成立していないと手続きが進められません。
遺産分割協議を早めに進めるためのポイント
遺産分割には法律上の期限はありませんが、相続税の申告期限である「10ヶ月」を意識することが重要です。
将来的に揉めそうな事情がある場合や、相続人が多数いる場合は、生前に以下の対策を取っておくと安心です。
遺言書の作成
誰にどの財産を相続させるのか明確に記載しておくことで、遺産分割協議のトラブルを防ぐことができます。
相続税対策の事前相談
専門家に相談することで、将来のトラブルを回避するための助言を受けることができます。
おわりに
遺産分割協議がまとまらない場合でも、相続税の申告と納税の期限は厳格に定められています。
申告期限までに遺産分割が成立しないと、相続税の軽減措置が使えなかったり、税負担が重くなったりとデメリットが多くなります。
そのため、相続が発生したらできるだけ早く遺産分割協議を進め、必要に応じて専門家に相談することが重要です。
また、将来の相続に備えて、生前の段階から遺言書の作成や相続税対策を行うことも、大切な家族への思いやりと言えるでしょう。
相続税申告や遺産分割に不安がある方は、ぜひお気軽に専門家にご相談ください。円満な相続と安心した手続きのために、私たちが全力でサポートいたします。
当事務所では、福岡を中心に北海道から沖縄までの全国を対応しております。
来所又はオンラインによるビデオ電話(Zoomなど)による初回無料相談を実施しております。
当事務所は博多駅から徒歩5分の好立地|税務・経営のお悩みをお気軽にご相談いただけます。
お気軽にお問い合わせください。

福岡市博多区にある久保税理士事務所では、相続税申告や事業承継、生前の節税対策など、個人・法人を問わず幅広いご相談を承っております。
初回のご相談は無料で受け付けておりますので、不安や疑問をお持ちの方も安心してお問い合わせいただけます。
福岡県全域はもちろん、佐賀県、山口県、長崎県、大分県、熊本県など九州各地、さらには全国からのご依頼にも対応可能です。また、オンライン面談にも対応しておりますので、遠方の方もお気軽にご相談ください。