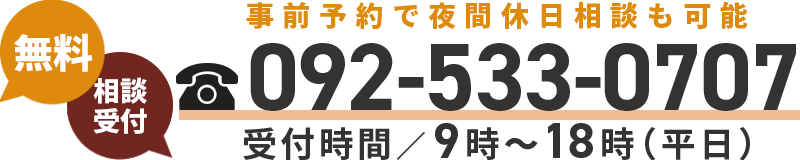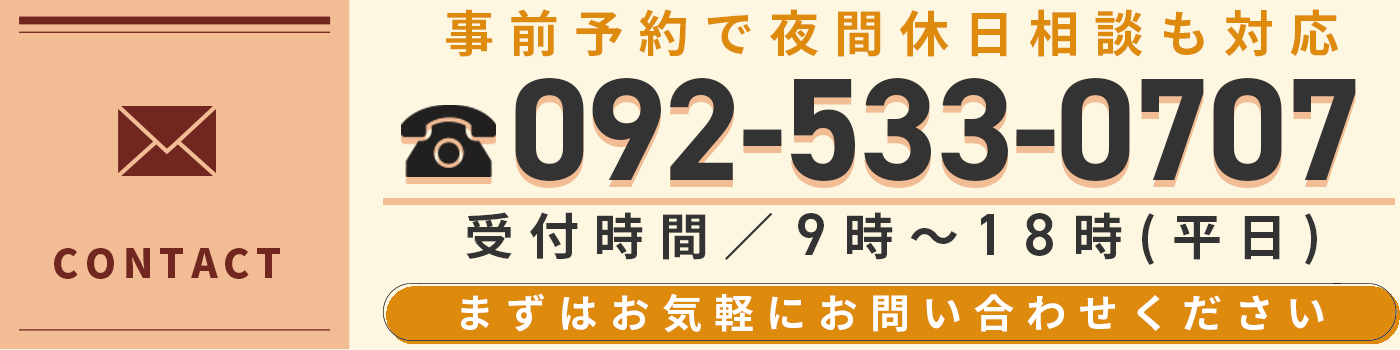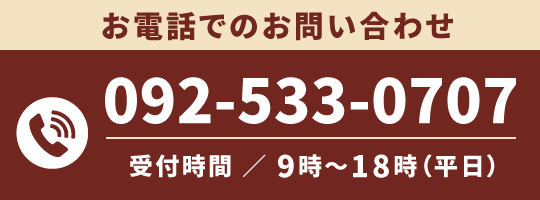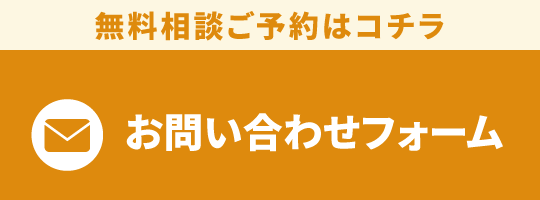このページの目次
はじめに
「親の遺産を受け取ったけれど、相続税の申告って本当に必要なの?」
「遺産がそこまで多くないから、申告しなくてもいい気がするけど、判断基準がよく分からない……」
このような疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。
相続税の申告が必要かどうかを判断するための第一歩は、「基礎控除額」と相続財産の総額を比較することです。
一見するとシンプルなルールですが、見落としや計算ミスがあると、後になって税務署から指摘を受ける可能性もあります。
この記事では、相続税の申告が必要かどうかを正しく判断するために、
- 基礎控除の計算方法
- 判断時に気をつけるべきポイント
- 相続税が発生しなくても申告が必要となるケース
を、わかりやすく解説していきます。
ご自身の状況を照らし合わせながら、適切な対応ができるようにぜひ参考にしてください。
相続税の申告は「基礎控除額」を超えるかどうかで決まる
相続税には「一定額までは申告不要」という仕組みがあり、それを「基礎控除」といいます。
この基礎控除額を超えない範囲の財産であれば、相続税が課税されないばかりか、申告自体も不要です。
基礎控除の算出方法は次の通りです。
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
たとえば、法定相続人の数が3人いる場合は、
3,000万円+(600万円×3)=4,800万円が相続税申告不要のラインです。
ただし、この計算をするには、財産の全容をしっかりと把握しておく必要があります。
意外と見落としがちな財産もあるため、慎重な確認が欠かせません。
申告の要不要を判断するための5ステップ
申告が必要かどうかを判断するには、次の流れに沿って確認していきましょう。
ステップ1:法定相続人の人数を確認する
法定相続人とは、民法の定めに基づき相続する権利を持つ人のことです。
配偶者は常に該当し、その他は下記の優先順位で確定します。
- 第1順位:子
- 第2順位:父母(子がいない場合)
- 第3順位:兄弟姉妹(子も父母もいない場合)
ステップ2:基礎控除額を計算する
確認した法定相続人の人数をもとに、基礎控除額を算出しましょう。
例)相続人が4人の場合
3,000万円+(600万円×4)=5,400万円
ステップ3:すべての相続財産を洗い出す
見落としがちな財産にも注意が必要です。
- 預貯金・不動産
- 株式・投資信託
- 車や宝石、骨董品などの動産
- 生命保険金や退職金(みなし相続財産)
- 債権(未回収の貸付金など)
さらに、借入金や未払金、葬式費用などのマイナス財産も含めて評価します。
ステップ4:相続財産の総額を計算する
洗い出した財産の評価額をすべて合算し、全体の遺産総額を算出します。
ステップ5:基礎控除額と比較する
相続財産の合計額が、基礎控除額を超えている場合は申告が必要です。
逆に下回っていれば、原則として申告不要です。
相続税が発生しなくても申告が必要な場合とは?
実は、相続税がゼロであっても申告しなければならないケースがあります。
これは、特例や控除を使って納税額がゼロになっている場合です。
具体的には次のような制度が該当します。
- 配偶者の税額軽減:配偶者の取得財産額が1億6,000万円または法定相続分のうちいずれか大きい金額以下の場合には相続税が課税されない制度
- 小規模宅地等の特例
- 農地の納税猶予制度
- 特定計画山林の特例
- 公益法人等への寄付による非課税措置
これらの特例を利用する場合は、たとえ納税額が発生しなくても申告書の提出が求められます。
判断ミスを防ぐための3つの注意点
「基礎控除の範囲内だから安心」と思い込むのは危険です。
以下の点に注意しないと、後から課税されるリスクがあります。
注意点①:見落とされやすい財産に気をつける
特に、名義預金(名義は家族でも管理実態が被相続人にあるもの)や、現金で保管されていたタンス預金などは注意が必要です。
税務署は金融機関への照会や過去の取引履歴からも調査を行います。
注意点②:相続時精算課税制度を使った贈与がある場合
生前贈与する場合には、特別控除の2,500万円までの贈与が課税されない「相続時精算課税」という制度があります。(令和6年1月1日以後の贈与は特別控除に加え基礎控除として年110万円があります。)。
この制度を利用した贈与は、相続時に遺産に合算されます。
結果として基礎控除を超える場合があるため、申告が必要になるケースも少なくありません。
注意点③:生前贈与の「持ち戻し」期間に注意
相続税の仕組みには、「生前に受け取った贈与財産も、相続財産として扱う」ルールがあります。「生前贈与加算(持ち戻し)」と呼ばれる制度で、被相続人(亡くなった方)が生前に行っていた贈与のうち、一定期間内の贈与分を、相続時の財産に加えて再計算するという仕組みです。暦年贈与が対象になります。
生前贈与加算の対象となる期間は「亡くなる前3年以内」とされていましたが、相続と贈与の一体課税の流れに合わせ、2024年(令和6年)1月1日以降の贈与分からは、対象期間が段階的に延長され、最終的には7年間に拡大されます。
この「持ち戻し」も忘れずに計算に入れておきましょう。
おわりに
相続税の申告が必要かどうかを判断するうえで大切なのは、「基礎控除額の正しい理解」と「財産の正確な把握」です。
簡単なようでいて、専門的な知識が求められるポイントも多く、自己判断で申告不要と決めてしまうのは危険です。
もし判断に迷ったら、相続税申告に精通した専門家に一度ご相談いただくことをおすすめします。
当事務所では、数多くの相続案件を手がけてきた経験をもとに、初回無料相談から丁寧にサポートいたします。
安心して相続の手続きを進めていただくためにも、ぜひお気軽にご相談ください。
当事務所では、福岡を中心に北海道から沖縄までの全国を対応しております。
来所又はオンラインによるビデオ電話(Zoomなど)による初回無料相談を実施しております。
当事務所は博多駅から徒歩5分の好立地|税務・経営のお悩みをお気軽にご相談いただけます。
お気軽にお問い合わせください。

福岡市博多区にある久保税理士事務所では、相続税申告や事業承継、生前の節税対策など、個人・法人を問わず幅広いご相談を承っております。
初回のご相談は無料で受け付けておりますので、不安や疑問をお持ちの方も安心してお問い合わせいただけます。
福岡県全域はもちろん、佐賀県、山口県、長崎県、大分県、熊本県など九州各地、さらには全国からのご依頼にも対応可能です。また、オンライン面談にも対応しておりますので、遠方の方もお気軽にご相談ください。