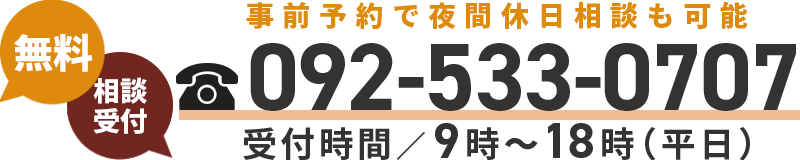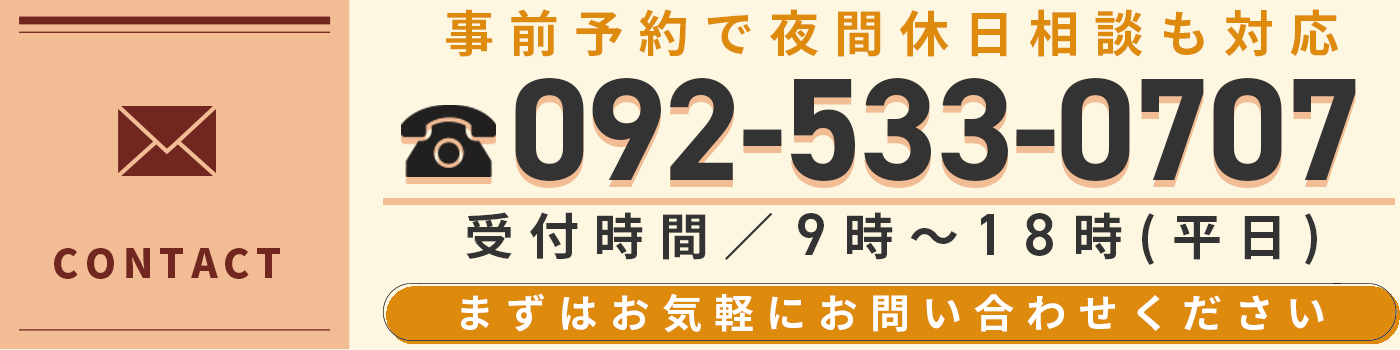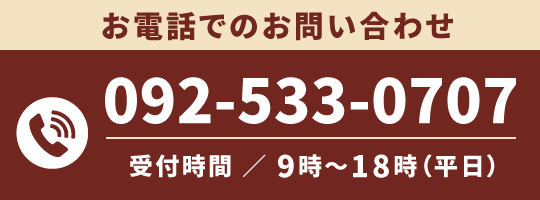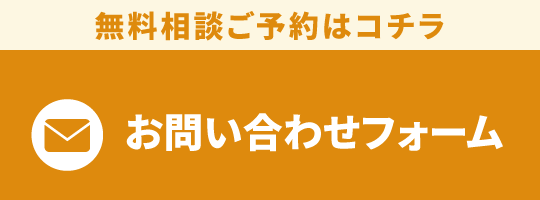このページの目次
はじめに
相続税について「納税額がゼロだから申告は不要」と誤解されている方が少なくありません。しかし、実際には相続税の申告が必要なケースもあり、正しく理解していないと大きな不利益を被る可能性があります。今回は、「相続税が発生しない場合でも申告が必要となるケース」について、具体例を交えながら解説いたします。
相続税の基本的な仕組み
相続税は、被相続人(亡くなった方)の財産の課税価格の合計が「基礎控除額」を超えると課税されます。この基礎控除額は、
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
で計算され、これを下回っていれば原則として納税義務は発生しません。
しかし、納税額が最終的にゼロであっても、「相続税の特例を適用した結果としてゼロになった」場合には、申告が義務付けられている点に注意が必要です。
相続税申告が必要となる代表的な特例
1. 小規模宅地等の特例を利用する場合
被相続人が所有していた土地について、一定の条件を満たすと評価額が大幅に減額される特例です。評価額の減額割合は以下のとおりです。
| 宅地の種類 | 限度面積 | 減額割合 |
| 特定居住用宅地等 | 330㎡ | 80% |
| 特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
| 貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% |
都市部など地価の高い地域ではこの特例の効果は大きく、特例を適用したことで納税額がゼロになることもあります。ただし、この特例は申告しなければ適用されないため、納税額がゼロでも申告が必要です。
2. 配偶者の税額軽減を受ける場合
配偶者が相続する財産については、以下の範囲内であれば相続税がかからない「配偶者の税額軽減」の特例が設けられています:
- 1億6,000万円まで
- または、配偶者の法定相続分相当額まで
この特例も、申告を行わないと適用できません。そのため、納税が発生しない場合でも申告が不可欠です。
申告が不要となるケース
相続税申告が本当に不要となるのは、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などの特例を適用せずに以下のような場合で課税価格の合計が基礎控除以下である場合です:
- 死亡保険金や退職金についての非課税枠の範囲内で収まっている場合
- 下記のような税額控除を使って相続税額がゼロになり、かつ申告要件が課されていない場合
- 贈与税額控除
- 未成年者控除
- 障害者控除
- 相次相続控除
- 外国税額控除
ただし、相続人が複数いる場合には、他の相続人と共同で申告を行うことが一般的ですので、申告義務がない方でも申告に関わる必要が出てくることがあります。
おわりに
「相続税がかからないから申告しなくていい」という考え方は、必ずしも正しくありません。特例の適用によって税額がゼロになる場合には、必ず申告が必要です。申告の有無が特例の適用の可否を左右するケースも多く、判断を誤ると多額の税負担を背負う可能性もあります。相続が発生した際には、専門家に相談しながら、適切な手続きを進めることが大切です。
弊所では、福岡を中心に北海道から沖縄までの全国を対応しております。
来所又はオンラインによるビデオ電話(Zoomなど)による初回無料相談を実施しております。
当事務所は博多駅から徒歩5分の好立地|税務・経営のお悩みをお気軽にご相談いただけます。
また、簡易株価算定を無料で行っておりますので、事業承継を検討されている方は、ぜひお気軽にご相談ください。

福岡市博多区にある久保税理士事務所では、相続税申告や事業承継、生前の節税対策など、個人・法人を問わず幅広いご相談を承っております。
初回のご相談は無料で受け付けておりますので、不安や疑問をお持ちの方も安心してお問い合わせいただけます。
福岡県全域はもちろん、佐賀県、山口県、長崎県、大分県、熊本県など九州各地、さらには全国からのご依頼にも対応可能です。また、オンライン面談にも対応しておりますので、遠方の方もお気軽にご相談ください。