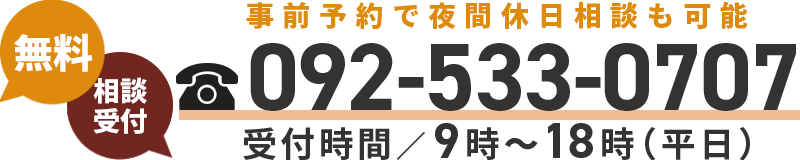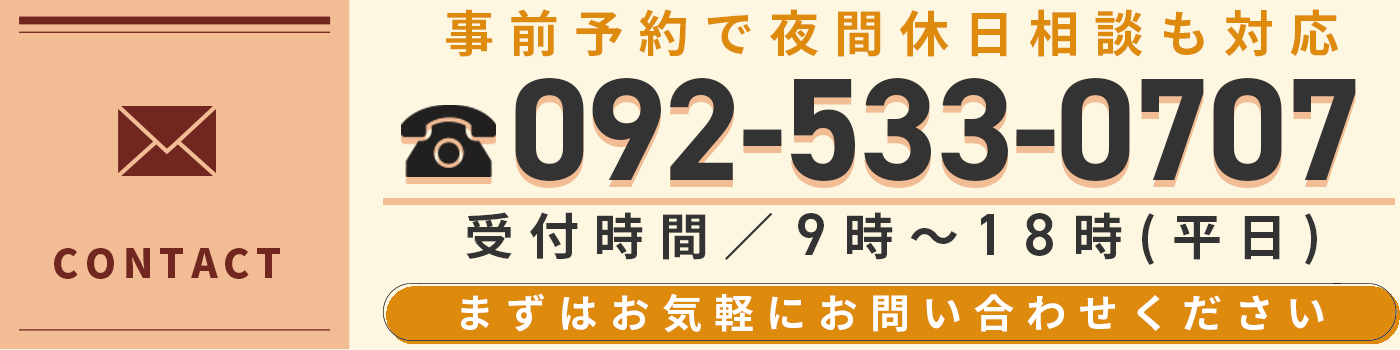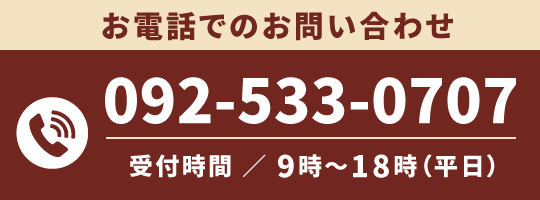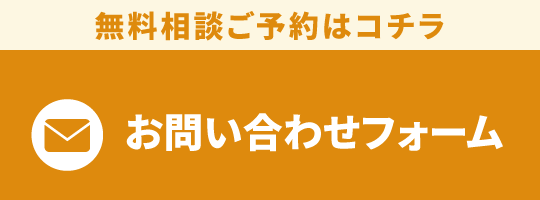このページの目次
はじめに
実家の整理をしていたら、思いがけず「金の延べ棒」が出てきた——。実際にそのようなご相談をいただくことがあります。金(ゴールド)は価値が安定している資産として知られていますが、相続に関しては正確な評価と適切な申告が求められます。
「金って相続税がかかるの?」「申告しないとどうなる?」と不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。結論からお伝えすると、金は相続税の課税対象となる財産であり、申告を怠ると高額な重加算税のリスクもあります。
本記事では、金の相続における評価方法や税金の仕組み、注意すべき税務調査の視点、さらには税負担を軽減する対策まで、実務のプロである税理士の視点から分かりやすく解説していきます。
金は相続税の課税対象。評価は「亡くなった日」が基準
金(ゴールド)を含む貴金属は、「金銭に見積もることができる財産」として相続税の課税対象に含まれます。評価方法は、被相続人が亡くなった日の業者による買取価格を基準とします。
金の評価方法
- 評価基準日:被相続人の死亡日
- 評価額:その日の金買取価格 × 重量(g)
宝飾品や仏具などに加工された金は、鑑定を通じて評価されます。専門業者の査定を受ける必要があり、自己判断では適正な評価が難しい点に注意が必要です。
相続税の基礎控除と課税のしくみ
金単体に対して税率が設定されているわけではなく、金を含めた全体の遺産額(不動産・現金・証券などを含む)に対して、一定の金額を超えると課税対象になります。
相続税の基礎控除額
【3,000万円+600万円 × 法定相続人の数】
たとえば、相続人が配偶者と子ども2人の場合は、
→ 3,000万円+600万円×3人=4,800万円が非課税枠になります。
この基礎控除を超える分が課税対象となり、相続税の計算が必要になります。
金を申告せずに隠すのは危険。税務署にバレる理由とは?
「金を自宅の金庫に保管していたし、税務署にはわからないのでは…?」
そんな考えは大変危険です。
税務署が金の相続を把握できる主な理由
- 金地金にはシリアルナンバーが刻印され、購入履歴が残る
- 売却額が200万円を超えると、業者が税務署に「支払調書」を提出
- 被相続人・相続人の預金出金履歴から金の購入が推測される
実際、金の相続を隠した場合、最大40%の重加算税が課せられる可能性があります。金は匿名性の高い資産と思われがちですが、相続時には税務署の厳しい目が光っていることを忘れてはいけません。
金の相続後に売却すると「譲渡所得課税」が発生することも
相続した金を売却した場合には、相続税とは別に「譲渡所得」が発生します。
この所得は通常、所得税・住民税の対象となり、所有期間によって計算方法が異なります。
金を譲渡した場合には総合課税の対象になります。
金を取得した時の「取得価額」が重要ですが、証明できない場合は、売却価格の5%が取得費とみなされ、税負担が重くなる可能性があります。
金の相続税対策として有効な「生前贈与」とは?
将来の相続税負担を抑えるために、生前贈与という選択肢も検討に値します。
年間110万円以下なら非課税
生前贈与は年間110万円までであれば非課税です。この範囲内で数年にわたり贈与を繰り返すことで、相続財産を減らすことが可能です。
相続時精算課税制度の活用
この制度を使えば、2,500万円までの贈与が非課税になります。ただし、相続時にその金額を含めて相続税の計算がされますので注意が必要です。
贈与の証拠(契約書・振込履歴)を必ず残しましょう。
手渡しや口約束では贈与と認められず、課税されるケースが多発しています。
金の仏壇や仏具を購入しても非課税にはならない?
「仏壇や仏具は非課税」と聞いて、金で作られた仏壇を購入しようとする方もいらっしゃいますが、華美な装飾や骨董価値のあるものは非課税と認められない可能性があります。
あくまで社会通念上、日常の礼拝に用いる程度であることが求められます。投資性のある仏具は課税対象と判断されますので、節税目的での購入はリスクが高いと言えます。
おわりに:金の相続は慎重な判断と正確な申告がカギ。専門家への早めの相談を
金の相続には、相続税の課税評価、税務署のチェック体制、売却時の所得税、贈与の落とし穴など、数多くのリスクと注意点があります。
もし「実家に金があったけど、どう扱えばいいの?」「相続税の対象かどうか不安」といったお悩みをお持ちでしたら、一人で悩まず、まずは専門家に相談することをおすすめします。
久保税理士事務所では、金や貴金属を含む相続財産に関するご相談を初回無料で承っております。
評価方法や申告の進め方、税務署への対応まで、丁寧にご説明いたします。
当事務所では、福岡を中心に北海道から沖縄までの全国を対応しております。
来所又はオンラインによるビデオ電話(Zoomなど)による初回無料相談を実施しております。
お気軽にお問い合わせください。

福岡市博多区にある久保税理士事務所では、相続税申告や事業承継、生前の節税対策など、個人・法人を問わず幅広いご相談を承っております。
初回のご相談は無料で受け付けておりますので、不安や疑問をお持ちの方も安心してお問い合わせいただけます。
福岡県全域はもちろん、佐賀県、山口県、長崎県、大分県、熊本県など九州各地、さらには全国からのご依頼にも対応可能です。また、オンライン面談にも対応しておりますので、遠方の方もお気軽にご相談ください。
税理士 久保 亮太のプロフィール